1〜2回戦
1回戦、牛飼いのノブと対戦したのはジュディスだった。本人に出る気は全くなかったのだが、マリエルが勝手にエントリーしてしまったのだ。
困り果てたのは当然のことである。
「頑張るのよ、ジュディス!」
励ましてもらってもあまり嬉しくはない。
「頑張れって……マリエル、勝手に……。あたしは出場なんてしたくないのに」
-- やっぱり出場辞退してくるわ。
言って歩きかけたジュディスの手を握りしめて、マリエルが耳打ちした。
「ジュディス。対戦表見たでしょ? 上手くすればあんた、3回戦で神官さまとあたるのよ。堂々と手を握れるこんなチャンスを逃す手なんて、ないわっ!」
ぴた。
ジュディスの足が止まって、回れ右。
「……ありがとう、マリエル。あたし、やるわ!」
そして数分後……ジュディスはマリエルのお小言をもらっていた。
「どうしてあんなにあっさり負けるのよ〜? あんた、試合が始まるまではあんなに気合い入れてたのに、始まった途端腕の力抜いたでしょ。どうしたのよ、ジュディス?」
-- 神官さまの手を握れなくてもいいの?
マリエルが視線で問いかける。
怒られても仕方がなかった。マリエルの指摘は当たっている。確かにジュディスは「始め」のかけ声と同時に腕の力を抜いたのだ。
「せっかくあたしがエントリーしてあげたのに。どうしてあそこで気を変えたのか、説明してごらんなさい」
呆れ顔のマリエルに、ジュディスはぼそっと小声で言った。
「……たの」
「え、何ですって?」
「だから、3回戦まで勝ち進んだら、神官さまに、馬鹿力の女の子って、思われないかなって……。そんな風に思われるのはイヤだなって、そう思ったの」
はぁ〜〜〜っ。
俯いたままぽつりぽつりと答える親友をじっと見つめて、マリエルはため息をつく。
(こんなチャンス、めったにないのに)
それでも、ジュディスの気持ちも判ってしまう。友達だから。彼女の想いを知っているから。そして、同い年の女の子だから。
乙女心は微妙なのである。
「あんたの気持ちも考えないで、勝手にエントリーしてごめんね、ジュディス」
「ううん。あたしこそごめんね。せっかくマリエルがエントリーしてくれたのに、無駄にして」
「いいのよ、そんなこと」
清純を絵に描いたような光景だった。
そこに、不純の固まりのような不良中年の声が割り込んだ。勿論サウルである。
「どうしたんだい、お嬢さん方? 哀しいことがあったんなら、おぢさんが慰めて……」
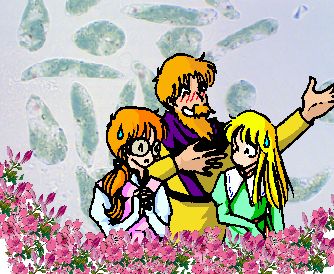
「結構です!」
冷たい声が背後から飛ぶ。
「彼女達に近づかないで下さい、隊長さん」
「神官さん……。近づくなって、人をばい菌みたいに……」
「こと女性に関しては、似たようなモノでしょう」
ジェニアスの言葉には容赦がない。
「神官さん……言うことがキツくなったね」
苦笑混じりのサウルに答えてジェニアス。
「悟ったんです、あなたにはこのくらい言わないとダメだと」
「……バカ神官も少しは学んだようだな」
「……カイル……」
ぼそっと呟いたカイルの台詞が、実は一番キツかった。
***
3人の間に漂う冷ややかな空気を吹き飛ばしたのは、靴屋のフィンだった。
「隊長、出番だよ。早く来ないと不戦敗になっちまうだよ」
「おお、今行く〜〜」
サウルが慌てて走って行く。
「頑張るだよ、隊長さん!」
「まかせとけっ♪」
自信たっぷりのサウルの台詞を聞いて、ジェニアスがカイルに話しかけた。
「何もしないと思いますか、カイル?」
「さてな」
2人の視線はサウルの手元に集中している。
-- 今度は何をやるのか……。
声に出すまでもなく、2人は同じ懸念を共有していた。
-- 何かが、変だ。
「おい」
「ええ。手袋ですね」
サウルは今、手袋をはいている。酒を飲んでいた時には、いや、ついさっきまでは素手だったにも関わらず、だ。
-- 何か仕込んでいるに違いない。
カイルとジェニアスの青と紫の瞳に、同じ思いが浮かんでいる。
前回サウルが使ったのは、鶏の小骨だった。対戦を始めた途端に、それを折ってポキッという音を立て、手の骨が折れたかと本気で心配した相手の隙をつくという、甚だ姑息なことをやってのけた。
勿論失格になったが、サウルのことだ。懲りずにまた何か考えているに違いない。
「隊長さん!」
-- 待ちなさい!
ジェニアスが叫んで止めようとしたが一瞬遅く、「始め」のコールがかかってしまった。そうして、その瞬間、サウルの口元がにやりと笑みを形作ったのである。

-- 今度は何を……?
だが、固唾を呑んで見守るジェニアスの予想に反して、サウルは対戦相手であるビール農家の親父と真面目に腕相撲を始めた。
「隊長、頑張れ〜〜」
「おやっさん、負けるなっ!」
不良中年とはいえ歴戦のサウルと、力には自信のあるビール農家の親父である。熱戦の予感に、周囲からかけ声が飛ぶ。
(今回は、真面目に腕相撲をやるつもりなんだろうか……?)
ジェニアスがそう信じかけた、その時。
「た、隊長っ、ち、ち、血がっっっ!」
ビール農家の親父が叫んだ。
「!?」
見れば、サウルの右の手袋と袖が赤く染まり、テーブルの上に同じ色の液体が水たまりを作っている。
「しまった……傷口が開いたか」
サウルの言葉に、対戦相手の親父はおろか周囲の観客までが慌てた。
「隊長っ、腕相撲なんてやってる場合じゃないだよ! 早く手当しないと……」
さあ包帯だ、その前に消毒だと、子馬亭の主が店の奥に駆け込みそうになる。が、その動きを、他でもないサウルの声が引き留めた。
「な〜〜んてね。うっそだよ〜〜〜ん♪」
言うと同時に、自分の右手に力をこめる。
ぱったり。
サウルの傷の心配をしていた相手は、当然、あっさり勝ちを譲ってしまった。
「……へっ?」
「隊長、怪我は……血は……?」
きょとんと呟く一同に、サウルは言ったものである。
「やだなぁ、よく見ろよ。血じゃねぇぜ、これ。ワインだよ、ワ・イ・ン。布にたっぷり赤ワインを染み込ませて、それをこうして手袋で隠してだな……」
手袋を取ると、なるほど右手には赤く染まった布が握られている。
滴るほどに赤ワインを吸わせた布を、手袋の中に仕込んでおけば、腕相撲で力を入れると嫌でもワインが手袋と袖を濡らし、テーブルに流れ落ちる。それを血と見間違えて対戦相手が驚けば、その隙をついて一気に勝ちに持ち込むという寸法だ。
姑息なことこの上ない。
だが、辺境の人々はおおらかだった。
「いや〜〜っ、ま〜たやられちまっただよ」
「この前は鶏の骨で、今度はワインだか」
「色々上手い手を考えつくだなぁ、隊長」
「どうやったらそんな手を思いつくんだ?」
流石、都育ちの軍人さんは違うだなぁ、あっはっは〜、と朗らかに笑って感心している。
「そりゃ、経験ってやつだよ」
調子に乗って自慢げなサウル。だが彼は、潔癖性の神官の存在を失念していた。
狐作物語集Topへ 続きを読む
|

