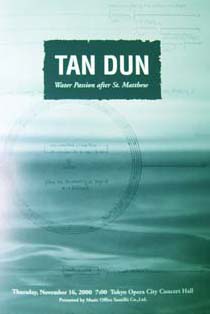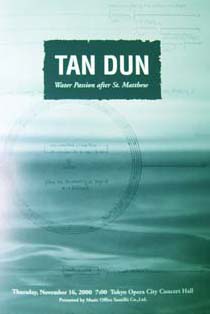 |
2000年11月16日(木)19:00/東京オペラシティ・コンサートホール
(演奏)
タン・ドゥン(作曲・指揮)
トッド・レイノルズ(ヴァイオリン)
マヤ・ベイザー(チェロ)
エリザベス・コーシュ(ソプラノ)
ステファン・ブライアント(バリトン)
デイヴィッド・コシン(パーカッション)
新澤義美(パーカッション)
塚田吉幸(パーカッション)
サラ・イオニデス(アシスタント・コンダクター/合唱指導)
ユアンリン・チェン(エレクトロニック・サウンド・デザイナー)
デイヴィッド・シェパード(サウンド・デザイナー)
二期会(合唱)
(プログラム)
タン・ドゥン作曲「新マタイ受難曲〜永遠の水」
第1部
1.洗礼 2.荒野の試み 3.最後の晩餐 4.ゲッセマネの園
第2部
5.石のうた(ペテロとユダ) 6.バラバを釈放せよ
7.死と地震
8.水とキリストの復活
|
--------------------------------------------------------------------------
タン・ドゥンと聞けばゴースト・オペラ「鬼戯」やオペラ「マルコポーロ」が思い出
される。特にマルコポーロではシルクロードを旅する壮大なドラマに圧倒されたのが
記憶に新しい。今回はバッハ・アカデミー委嘱で作曲された新マタイ受難曲の日本初
演というから、これは絶対に見逃せない。
プログラム解説にはタン・ドゥンのコメントが記されているが、彼の解釈ではキリス
トの復活を水の循環に喩えているらしい。水の循環とは雨が降って、これが水蒸気と
して上昇しまた降って来るというもの。もっともこういったアイデアは観念的するぎ
るといった批判もあるかと思うが、タン・ドゥンの素晴らしいところは、形而上のア
イデアに留まらず、身のある音楽、この場合はマタイというドラマで迫ってくること
だと感じた。
ステージには17個のウォーター・ティンパニが十字架状にレイアウトされている。
水の入った大きなガラス・ボウルの楽器だ。手で水をすくって、滴り落ちる水音をス
ピーカーでアンプリファイする仕組みになっている。時に金属板を水に沈めてティン
パニのように叩いたりして、独特の音色を放つ。これが結構ダイナミックな音響で、
よくもここまで変幻自在の音をだせるのかと驚く。
指揮者の位置がウォーター・ティンパニの十字架の頭に位置し、そのままステージ後
方へ9個のボウルが並ぶ。一番奥にパーカッション群を配置し、十字架左右の両端に
もそれぞれティンパニが配列される。ちょうど十字架でステージが4分割されること
となるが、後方左ブロックはソプラノとアルトによる女声合唱、右ブロックはテノー
ルとバスによる男性合唱となる。前方左ブロックにバリトンとヴァイオリンのソロ、
前方右ブロックがソプラノとチェロのソロが配置される。音楽編成的にはバッハのマ
タイと同様2部オーケストラの構造を持ち、これが十字架と有機的に結びついている
のが面白い。
照明が全て消され、完全な闇の世界から音楽が始まった。最初に聞こえてくるのは水
の滴る音である。二人のパーカッション奏者は客席左右の後方から不思議な楽器を奏
でながら登場した。第1部洗礼はまさに水の音が支配する世界。次第にソプラノのソ
ロが加わり、コンテンポラリな音響世界を形づくっていく。普段耳にしない音楽では
あるが決して拒絶反応はない。瞑想的な音楽に安堵感すら感じられる。荒野の試みで
は凶暴なリズムに魅了された。このリズムはウォーター・ティンパニをはじめとする
パーカッションで作り出されるが、アタックの強い合唱も素晴らしい効果をあげてい
た。ゲッセマネの園にいたっては原色の色彩を感じるほどの魅力に溢れる。ドラマの
テキストは全てマタイ福音書によりながらも、コラールに該当する個所はタン・ドゥ
ンの簡単なテキストが書き加えられている。
いわゆるマタイ受難曲という伝統的な宗教音楽という規範からは想像もつかないほど
の強烈な音楽ではあるが、タン・ドゥンのマタイは人を捉えてらえて放さないほどの
集中力に富んでいる。特に第2部からは迫真のドラマとなるが、タン・ドゥンの音楽
も然り。ペテロとユダのくだりは二つの石をすり合わせる音を伴奏として進められる。
とにかくヴァイオリンとチェロの演奏の凄さには驚嘆。激しいリズムとパッセージに
聞き入ってしまう。イエス役のブライアントはチベット特有の発声ホー・ミーも織り
交ぜながら肉薄したドラマを演じたのが素晴らしい。コーシュのソプラノも複雑なパ
ッセージを巧みにこなす。イエスの死にかけての壮絶な音楽はかなり強烈だ。特に地
震の描写は恐怖すら感じられる。しかしフィナーレとなるイエスの復活のくだりでは、
今までの重圧的な暗い世界が一転し、ユートピアを思わせる幸福の音楽となった。チ
ベットの楽器の奏でる天国的な響きとリズム。男声合唱を中心に繰り広げられるコラ
ールの荘厳さとともに感動が高まる。照明が次第に落とされ、光輝くウォーター・テ
ィンパニ17個が演奏者たちによって水の音を奏でる。ステージはただ至福への希望
に包まれた十字架が輝いてる。ウォーター・ボウルも光を次第に失い、ようやく水音
が消えたところでドラマは完結した。
照明効果や特殊奏法に訴えるコンテンポラリ音楽は紛いものと思われるがちだが、こ
の作品は決して紛いものではない。バッハのマタイを超えたと評されていることに頷
ける。バッハの荘厳で宗教的な高みとは次元を異にするものの、タン・ドゥンの作品
もこれに匹敵するほど感動的かつ音楽的な作品だと言えるだろう。特にフィナーレの
感動はひとしおで、心を浄化される思いにさせられた。しかし今日のコンサートは強
烈な印象を与えてくれた。ちょうどパルジファルの神聖な衝撃を受けたような感覚だ。