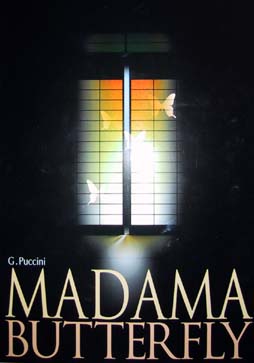
演出:ケレニー・ガーボル=ミクローシュ
指揮:パール・タマーシュ
蝶々夫人:川副千尋
スズキ :ヴィーデマン・ベルナデット
ピンカートン:グラーシュ・デーネシュ
シャープレス:ミラー・ラヨシュ
ゴロー :デレチュケイ・ジョルト
ヤマドリ :マルティン・ヤーノシュ
神官 :ラーツ・イシュトヴァーン
プラハ国立歌劇場管弦楽団・合唱団
●ハンガリー国立歌劇場/プッチーニ作曲『蝶々夫人』
2000年10月22日(日)14:00/オーチャードホール
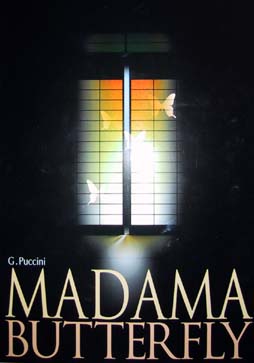 |
演出:ケレニー・ガーボル=ミクローシュ |
オーチャードで蝶々夫人を見るのはこれが2回目。前回は若杉弘指揮によるもの
で、シンプルで美しい舞台セットが印象に残っている。今日の舞台もシンプルで、
素晴らしいと思った。このオペラには色んな舞台があるにしても、大抵は透けた
日本家屋を基本にしている。決して石造りの建物は出てこない。後は障子や屏風
がお決まりだ。しかしハンガリーの舞台は背景と両サイド側面を巨大な障子にす
るという大胆さ。ちょうどこれはクプファーのマクベスやワルキューレで見られ
るようなキュービックな巨大壁にも似ている。ユニークなのは障子全体にシルエ
ットを映し出したり、幻想的な照明でもってドラマを語ることにある。
特に照明効果はグラフィック・アート調でもあり、どこかロバート・ウィルソン
の演出手法を思わせる。それでいて人物は静止状態というわけでもなく、実に生
き生きとした描写を行う。時に脇役たちを静止させることによって、場面の意味
を克明に強調するあたりに逆説的演出の上手さを感じる。
そして何よりも舞台のシンプルさがドラマを邪魔することなく、的確な照明が蝶
々夫人の情感を浮かび上がらせていた。また舞台中央の神木がどっしりと立って
いるのが強烈なインパクトを与える。何気ないようであるが、全幕とおしてドラ
マを引き締めるシンボルとなっている。けなげな蝶々夫人が祈るのは日本の神で
はないにしても、この神木に蝶々夫人の芯の強さがオーバーラップして見えてく
るようだ。それほどに今日の上演は舞台、歌手、管弦楽が緻密に融合していた。
もっともハンガリー国立にトップレベルの公演を最初から期待していなかったが
期待を上回る内容だったと思う。これはやはり川副の素晴らしさとオーケストラ
の一体感、集中力に負うところが大きい。彼女の歌が単に凄いという訳ではない
が、歌を感じさせない自然さ。まさに蝶々夫人になりきった歌というものが素晴
らしい。これに呼応しあう管弦楽の起伏の大きさもまた格別。最初はアンサンブ
ルの粗さがやや気にはなったが、聴きこむほどに実に雄弁にドラマを語るアンサ
ンブルに納得する。やや誇張気味かと思うほどの照明効果とあいまってとても輪
郭のはっきりとした蝶々夫人の魅力に惹きこまれた次第。その意味において日本
を題材としたドラマではあっても随所に西欧的描写を感じた。いずれにせよプッ
チーニが目指したであろうマダム・バタフライに接することが出来たのではない
だろうか。