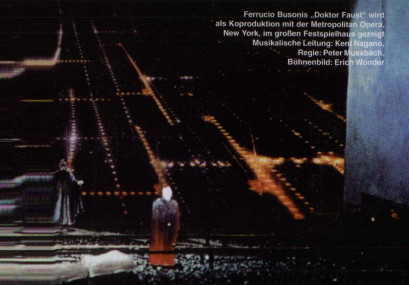
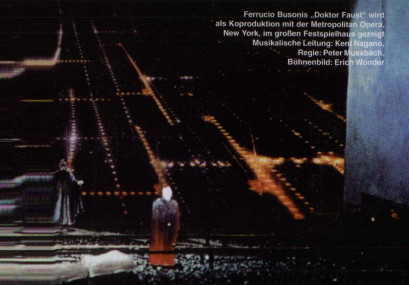
08/01 ザルツブルク音楽祭『ドクター・ファウスト』
●Ferruccio Busoni
DOCTOR FAUST
Premiere 1.August 1999, Grosses Festspielehaus
Musikalische Leitung : Kent Nagano
Inszenierung : Peter Mussbach
Buehnenbild : Erich Wonder
Kostueme : Andrea Schmidt-Futterer
Licht : Konrad Lindenberg
Choreinstudierung : Donarld Palumbo
Doctor Faust : Thomas Hampson
Mephistopheles : Chris Merritt
Wagner : Laszlo Polgar
Herzog von Parma : Kurt Schreibmayer
Herzogin von Parma : Katarina Dalayman
Des Maedchens Bruder : William Dazeley
Ein Leutnant : Guy Renard
Drei Studenten aus Krakau : Thomas W. Kuckler, Markus Eiche,
Bernd Hofmann
Theologe : Marek Gasztecki
Jurist : Markus Eiche
Wiener Philharmoniker
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Buehnenmusik : Mozarteum Orchester Salzburg
-----------------------------------------------------------------------
今回のブゾーニ「ドクター・ファウスト」は渋い演目ながらも、プレミエとあっては祝祭劇場もさすがに華やかだ。この作品は一般のファウストのお話とさして違いはない。オペラではファウストを題材とするものが多く、グノー、ベルリオーズやボーイトなどが有名である。しかしブゾーニとなると上演される機会は極めて少ない。それゆえに今回の公演はとても貴重だ。
SPECTAKELという雑誌に演出家ムスバッハが解説を載せている。これによるとファウストとはミスターXの空想の世界であり、もっと詳しく言えば、ブゾーニ自身をファウストとして焼きなおした物語とのこと。ミスターXとは未知の人という意味であり、万人を指していると解釈できる。さらにファウストの物語は妄想への旅と指摘する。ファウストが若返りと美しい女性へ憧れるのも妄想によるもので、パルマ侯爵夫人への愛は幻覚に過ぎないそうだ。
ムスバッハの解説はひとつの参考として、実演を見たかぎり今回のオペラはかなりの成功と言えるだろう。彼のオリジナリティ溢れる個性が随所に見られるのと同時に、ファウストの世界に聴衆を引きずり込んでしまう求心力に感心した。
第1幕、ファウストの書斎は閉ざされた四角い空間で描かれる。左右に開かれた小さな穴が唯一外界との接点となっており、既にこの器が自閉症者ファウストをイメージしている。左右の穴には2車線のレール走っていて、3人の学生がトロッコで登場。このトロッコに魔法の本と鍵それに契約書が載っている訳だが、これは2001年宇宙への旅で登場したモノリスのミニチュアサイズのようだ。注目すべきはファウストとメフィストフェレがとても良く似ていること。共にフロックコートにシルクハットという姿。さらに彼らが語合うときは左右のトロッコの上で対照形をなしていた。まるでファウストの分身としてメフィストが存在するかのように見えた。おそらくファウストの内面にメフィストが居ることを意味しているのだろうか。
このような視点で見ていくと続く第2場でメフィストが殺人を犯す場面も、これがファウストの意思であることが容易に理解できる。ハンプソンも老人ファウストを見事に演じ、メリットのメフィストも滑稽ながらもドスの効いた凄みがあった。
パルマ侯爵の結婚式では見事な舞台に唖然とさせられる。中央部から天高くまで山のこぶが連なっている。こぶこぶから侯爵と侯爵夫人、合唱が姿を現す場面などは2年前の「ルーチョ・シッラ」にも共通する手法でありムスバッハらしい。この場面でファウストは若返り、ハンプソンの変身ぶりが見物だった。さらに舞台は、地球の地平線をバックに宇宙を描いたセットに変貌。まさに息をもつかせないテンポでドラマが展開して行く。
ヴィッテンベルクでファウストがメフィストに裏切られる場面では世間の目を象徴するかのような「大きな目玉」が登場する。これなども多分に説明的ではあるが、全体に無駄のないシンプルな演出に統一されている。驚いたことに登場人物が炎を纏って歩き回っていたが、これなどは特殊な防火服を用いているのだろう。
さてブゾーニの音楽はロマン派のなごりを残しつつも、ベルクと同様に20世紀である。総じてドラマとの融合を特徴とし、とても美しいと感じた。アリアこそ無いが、語りや叫びとハーモニーする不思議なタイプの音楽でもある。座席は最前列中央のケント・ナガノ氏のすぐ間際だったので、彼の指揮振りをつぶさに観察できた。氏の気合はかなりのもので、時折その気合が唸りとして聞えてくる。ナガノ氏の温厚な表情からは信じられないくらい厳しい気合が漲っていたのが印象的だ。彼の気合はそのままオーケストラの気合となっているのが良く分る。ちなみにコンサートマスターはキュッヒュル氏で、そのソロは幻想的かつ美しいものだった。
歌手ではハンプソンがいうまでもなく歌と演技で最高の出来映えだ。メリットの悪役ぶりも上手い。ダレイマンは5月のバスチーユで「ヴォツェック」のマリーを見たが、今回は役柄上、歌の聞かせ所が少なかったのが残念なところ。ブゾーニのこのオペラではパルマ侯爵夫人の出番が少ないのだ。
さて本公演はメトロポリタンとの共同製作だそうで、METでも上演される予定。METでも上演できように、前半の舞台では祝祭劇場の広いステージが全て使われず、左右が幕でカットされていた。カーテンコールも盛大でナガノ&ウィーンフィルのコンビへの成功を告げるものであった。ムスバッハ氏も登場し演出の素晴らしさを絶賛するカーテンコールとなった。かくして斬新なオペラに興奮し、8月1日は充実感満点の一日であった。