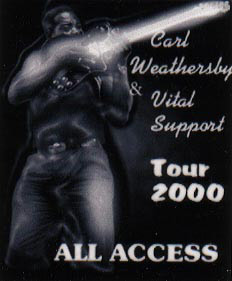私が、初めてカールに会ったのは1991年のことだった。
自称ハーピストの私は、長年の夢であったビリー・ブランチの演奏が聴きたくてシカゴのサウス・サイドへと向かったのであった。
私は、ビリーのハーモニカに驚喜した。流れるように構成された「ショー」に感心し、黒人街の洒落たクラブの雰囲気に酔いしれ、そして時間を忘れていた。ギグの合間にビリーに話しかけ、一緒に写真を撮ってもらい、酒を飲んだ。
そのバンドのギタリストは、カール・ウエザスビーという体の大きな男であった。ビリーとは対照的に、黙々とギターを弾き、演奏する曲もスロー・ブルースやソウルの有名曲が主体であった。しかしそのギター・プレイは鋭く、歌声はビリーやドラムスのモーズとは比べものにならないほどソウルフルであった。
私は彼に話しかけた。
「私は、あなた達の演奏を聴きたくて東京から来ました」
「フーム...」
「素晴らしいギター・プレイとヴォーカルですね」
「サンクス...」
取っつきにくい男だなぁ、というのが第一印象であった。
92、93年と続けてシカゴに行ったが、ビリーやベースのメルヴィンとの親交は深めることが出来ても、カールとは相変わらず一言二言声をかけるのみに留まっていた。
しかし私は、彼の魅力にますます引き込まれていった。92年作の「Mississippi Flashback」を聴いてもらえれば分かっていただけると思うが、ある時はビリーを引き立てる役に回り、自分がフロントに廻ったときはディープでソウルフルな世界を展開する。それはスリルあふれる素晴らしいパフォーマンスであった。
そんな私とカールとの関係(?)に変化が訪れたのは、94年シカゴでのことであった。
シカゴ・ブルース・フェスティヴァルの会場となっていた、広大なグラント・パークを歩いていたら、背後から声がかかった。
「ハイ!ヒロ!!どこ行くんだい!?」
「うわー!カール!」
いつの間にか彼は名前を覚えていてくれたのだ。このときは本当に嬉しかった。
ちょっと前の、S.O.B.のステージの時に、小さな女の子がカールの横に座っていたこと思い出し、そのことを聞いてみた。
「さっきステージに座っていたのはあなたの娘さんかい?」
「そうだよ」
「かわいい娘だね」
「サンキュー!」
彼が初めて私に見せた笑顔であった。

Chicago Blues Festival 1994
94年の7月に、S.O.B.は「スミソニアン・アメリカン・フェスティヴァル」の一環として再来日を果たした。この時は、ビリーとカールを連れて東京のブルース・クラブ巡りをした。カールも喜んでくれたようだが、会話の中心はあくまでもビリーの方であった。
寡黙でクール...。それがカールの印象であった。
そんなカールが、自己バンドを率いて来日するというニュースを聞いたときには飛び上がらんばかりに喜んだ。
94年以来シカゴに行っていない私は、彼のソロCDは聴いてはいたものの、独立後のステージを観る機会を得たいと願っていたからだ。
私は彼に手紙を書いた。「あなたの来日を心待ちにしている」と。
驚いたことに、彼からの返事はe-mailであった。
「娘の方がコンピューターの扱いは上手いんだがな」としながらも、「ハロー、ヒロ!永らく会ってなかったなあ。東京で会うことを楽しみにしてるぜ!」とそこには書いてあった。
嬉しい返事ではあったが、果たして彼は私の顔を覚えていてくれてるだろうか。
偽らざる私の気持ちであった。
2000年5月24日(水)
ブルース・マーケット誌のインタビューを高橋'Teacher'誠氏が行うということで、都内某所のホテルのロビーに2時に集合することにする。
大阪、名古屋と公演を終えたカールは、きょう東京入りするらしい。いよいよカールと再会できるのだ。
時間前にロビーをうろついていると、50メートルほど先に立っていた巨大な黒人と目と目が合う。
「ハイ!ヒロ!」
「イェ〜イ!カール!!」
嬉しいことに彼は私を覚えていてくれた。むさい男同士が抱き合い、再会を喜び合う。
「これからインタビューなんだ。一緒に来るかい?」
「もちろん!」
初めからそのつもりだったのだが、行きがかり上「同席させてもらう」形になってしまった。
インタビューでは初めて聴かせてもらうような興味深い話もあったが、これは8月1日に発売されるブルース・マーケット誌No.23に掲載される予定なのでお楽しみに!
さて、インタビューが終盤にさしかかった頃、Teacherが録音用のDATのテープをひっくり返した。それを見たカールは、目をまん丸にし、
「なんだ、この小さなテープは?」
「DATっていうんだよ」
すっかり、この小さな魔法の箱に魅入られたカールは、DATを買いに行きたいという。さらに、SEIKO製のギターのボディーに張り付けることが出来るチューニング・メーターを探しに行きたいという。
何でそんなものが必要なのか不思議に思ったが、お茶の水までブラブラ散歩がてら歩くことにする。
道中のカールは、あっちをキョロキョロこっちをキョロキョロ落ち着きがない。物珍しいのかと思っていたら、「一人でもいけるように道を覚えている」とのこと。
「必要ならまた案内するよ」と伝えたが、本人は一生懸命道順を確認しているようだ。
お茶の水に着き、くだんのチューニング・メーターを探すことにする。ところがどこの店にも置いていない。店員に聞いてみると、「聞いたことはあるが、日本には入ってきていないと思う」とのこと。ガッカリしたカールだが、小型のチューニング・メーターをかわりに購入していた。
ところが、本人の興味は既にDATの方に向けられていたらしい。
「ヒロ。秋葉原は近いのかい?」
「すぐ近くだぜ」
「よし、行こう!」
かくしてカール様御一行は総武線に乗り秋葉原へと向かったのであった。
ところが、いくら世界の秋葉原とはいえ瀕死の状況にあるDATのポータブル・プレイヤーを置いてある店は数少ない。あるのはMDばかりだ。
「これはなんだい?」
「ミニ・ディスクだよ」
「....」
人から聞いた話だが、アメリカではMDというのはまだまだポピュラーではないらしい。あまりの商品の多さに、眉間にしわを寄せてしばらく考えていたカールは、「出直すことにしよう...」
「気持ちは分かるよ」と思わず笑ってしまった。
余談だが、カールはDVDプレイヤーに映し出されていた谷間を低空飛行するヘリコプターの画像(映画「アウト・ブレイク2」)に見入っていた。
「こんなヘリコプターに乗ったことがあるのかい?」
「もちろん」
彼は、6年間アメリカ陸軍に在籍し、ベトナムにも行った経験を持っているのである。

ホテルに帰るために駅に向かうと、秋葉原デパートの前で秋葉原名物「街頭販売」をやっていた。言葉巧みに商品を売る例のパフォーマンスである。
「こいつはなかなか面白いぜ」というとカールも興味ありげな様子。ホチキスの様な形の器具に電池を入れ、開封した袋(お菓子など)の開封部をなぞると、ピッタリとくっついてしまうという代物である。
クライマックスは、販売員のおやぢが水を入れた袋を取り出した時にやってきた。中央にその器具を挟み、上から下へゆっくりとなぞると、アラ不思議!なんと水が入ったままその袋がパッカリと二つに分かれたではないか!?
「うわ〜!凄いなあ!?」と言いながらカールの方を見ると、すでに彼は真剣な顔をしてポケットをまさぐり、金を出そうとしている。
「おい、ヒロ!こいつはいくらだ!?」
いやー、笑った笑った。こういうヤツが騙されて買っていくのね。大笑いの我々をよそ目に、魔法の器具を手に入れご満悦のカールくんであった。

ここでTeacherと別れ、ホテルの部屋へと戻り、ムーニーさんからプレゼントされたという「ブルース・テレキャスター」を見せてもらう。菊田俊介氏のテレキャスターと同型のもので、Carl
Weathersbyというサインが入っている。ボディはパーシモン、ネックはメイプル(珍しいトラ目)、ヘッドはオールド・テレキャスターの形をしているという。
それにしても美しいギターだ。今回メインに持ってきたギターは、HeritageというメーカーのES-335に似たモデル(B.B.
Kingスタイルのスイッチにしてある、とは本人の談)だが、東京ではブルース・テレキャスターの方をメインに使用していた(大阪、名古屋ではどうであったのだろうか)。
カールがブルース・テレキャスターを掴み、ブルースを弾き始める。すかさず私はハーモニカを取り出し、ジャム・セッションの始まりだ。
それにしても強力なシャッフルのリズムである。吹いていてメチャクチャ気持ちがいい。カールをバックにハーモニカを吹けるなんて、いやー役得。

さて、しばらくすると、カールがソワソワしだす。
「試合開始は何時だったっけ?」
そう、彼は根っからの野球好きで、今回の来日に際しても東京ドームに連れていく約束をしていたのだ。
昨夜も名古屋ドームに中日戦を見に行ったらしいが、今夜はファイターズ対ブルー・ウェーブだ。本当はジャイアンツを見たかったらしいのだが、この時期東京ではゲームがない。あったとしてもチケットなど取れるわけがないし、何よりもブルー・ウェーブ・ファンの私としてはイチローの雄志を彼に見せたかった。
すでに試合開始時間を過ぎていたので、タクシーに乗り一路東京ドームへ。三塁側の内野席に席を取りさっそくゲームを楽しむ。
それにしてもカールは本当に野球が好きである。バッター・ボックスとスコア・ボードを交互に睨みながら固唾をのんで見守っている。
この日のイチローは、一打席目二打席目は凡退に終わった。彼のことを「素晴らしいバッターだ」と伝えていただけに、カールは物足りない様子。
試合も中盤をすぎ、トイレに行きたくなった私は「トイレに行ってついでにタバコでも吸ってくるわ」と席を立つ。すると、カールも我慢していたようで後をついてきた。
「あー、いい気持ちだー」などと言いながら用事を済ませていると、観客の大歓声が!
「ど、どうしたんだ!?」と慌てて戻ると、なんとイチローが二塁に立っているではないか!思わず二人で目を合わせ、
「Bull Shit !!」
結局試合は、7回に田口の逆転二塁打などがあり、ブルー・ウェーブの勝利に終わり、気分良くホテルへと戻る。
「イチロー!」という声援をいたく気に入り、連呼していた。

ホテルに戻ると、そこには東京公演を終えたバディ・ガイ・バンドの一行が、ロビーにたむろしていた。
トニーZの姿を見つけ、カールに「あれは、トニーZじゃない?」と聞くと、
「知らねえなあ...」
しばらく他の人と話をしていると、カールが後ろから私を呼ぶ。
「ヘイ!ヒロ。トニーを紹介するよ!」
かくして、東京の一日目の夜は更けていくのであった。
2000年5月25日(木)
今日は目黒のブルース・アレイ・ジャパンでカール・バンドの単独公演が行われる。昼間は特に何もないということなので、私は一時帰宅をして会場で落ち合うことにする。
開演30分前くらいにブルース・アレイに着くと、入り口の前の道路にマネージャーのテッドが立っていた。彼は、シカゴのキングストン・マインズのサウンド・エンジニアも務める25歳の若者だ。
さっそく楽屋に案内され、バンドのメンバーを紹介してもらう。
ギターにポール・ヘンドリックス、ベースにカルヴィン・ガスキン、ドラムにジェシー・ワッツ・ジュニアという布陣だ。ギターのポール以外は全員黒人だが、どの顔も名前も覚えがない。聞くと、ブルースなんて知らなかったメンバーを集め、カールがトレーニングしてここまで育て上げたという。ギターは一度メンバー交代があったらしいが、後の二人はカールがソロ・デビュー以来のオリジナル・メンバーとのこと。メンバー交代がないこと自体がシカゴでは珍しく、それだけにバンドとしてのまとまりには自信があると言っていた。
M&Iの担当の方がやってきて「あと10分で開演します」と伝えていく。カールはおもむろにステージ用の金ぴかの時計を腕に巻き、楽屋には心地よい緊張感が走るのがこちらにも伝わってくる。
いよいよ、待ちに待ったカール・バンドのショーが始まるのだ。
開演時間が近づき席に戻ることにする。満席とはいえ、全部で100人ほどの入りだろうか。広い東京でたったの100人...。知った顔もほとんど見かけなかったし、う〜ん、もったいないなあ。
程なくカール以外のメンバーが登場し、セッティングを始める。自分の気持ちが高揚していくのが分かる。
そして、遂にショーの幕は切って落とされた。
まずはドラムのジェシーがボーカルを取る。曲はつい先日亡くなったジョニー・テイラーの「ホワット・アバウト・マイ・ラブ」。彼の歌もなかなかのものだ。
ワン・コーラスを歌いきったあたりだろうか。ポールはカッティングに専念しているのに、ギターのオブリガードが入っているのに気がつく。他のみんなも気がついたのか会場が徐々にざわつき始めた頃、座席後方からワイヤレスを抱えたカールが登場!
いやー、ありがちな演出とはいえ初めから鳥肌が立ってしまった。
1曲目が終わり間髪を入れずに、でたー!「キリング・フロア」のイントロだー!ギュイ〜ンと粘りけのあるギターを派手に弾き始めたと思ったら、5小節目の頭でバンッ!と音を落とす。降参です。参りました。
この曲では、ポールもソロを取ったが、推定200キロはあろうでかい腹(ちなみに身長は160センチ台)にギターを乗せ、カールそっくりの切り込みの良いギターを聴かせていた。
3曲目は「ルッキング・アウト・マイ・ウインドウ」だ。弦を切ってしまったがお構いなしに弾きまくり、4曲目はギターを持ち替えブルーム調のインストに入る。ところがここでも弦を切ってしまい、すかさずスロー・ブルースに切り替える。
何とここで、カールは歌いながら弦を張り替える荒技を披露した。Ktateさんが既に報告済みのように、コールの部分で歌い、レスポンスの部分で作業をするのである。この時初めてあのチューニング・メーターを探していた理由が分かった。この日は、弦の張り替えには失敗したが、土曜日の日比谷では見事に成功。みんなからの喝采を浴びていた。
しかし、カールのショーマン・シップは凄い。衣装はお揃いのものを揃え、お決まりのステップを全員で踏む。グッと音を落とし、再び盛り上げる際に、両脇のポールとカルヴィンが膝を腰の位置まで上げるステップを踏んだときには思わず大声を上げて声援してしまった。
実は、カールは両膝の具合が悪い。普段歩くときは膝をかばうようにゆっくりと歩くのだ。アメリカン・フットボールをやっていたときの古傷らしいが、ステージ上ではそんなことはおくびにも出さない。
そして、弦が切れるというアクシデントさえも観客を楽しませる材料にしてしまい、更にはMCを廃した流れるようなステージング...。聴覚だけではなく、視覚にも訴える見事な構成だ。カールの言っていた「バンドとしての一体感」とはこのことを言うのであろうか。
かと言って、リハーサルを積んだ演奏を、ただそのまま忠実に再現しているのとはまた違う。演奏中、バックのメンバーはカールを注視し、彼が次に何をやるのかしっかり見定めようと必死であった。それが心地よい緊張感を生むのである。
後日談になるのだが、この日の演奏曲をUPしようと思い、カールに「ソングリストはあるか」と聞いたら「ソングリスト?そんなものは無いよ。その場その場で考えながらやっているんで、何やったか忘れちゃったなあ」とのこと。全く持ってごもっともで御座います...。
ステージも中盤に入り、彼らはシカゴ・スタイルのミディアムなソウルナンバー「リープ・オブ・フェイス」をやった。ソロ2作目の「スウィート・ミュージック」に似た感じの、思わず手拍子をしたくなる軽快な曲だ。カールは、本当にこの手のテンポの曲が好きである。
ソウルナンバーを続けた後、この日の山場でもあるジョン・ハイアット作の「フィール・ライク・レイン」に突入。本人は「ジョン・ハイアットなど知らん」そうだが、バディ・ガイがやっているのを聴いて気に入ったという。この曲のコード進行が大好きだとのことだ。
CDのバージョンも原曲とはかなり違う雰囲気を持っていたが、この日はグッとテンポを落とし、かなりソウルフルにアレンジされていた。大げさではなく思わず目頭が熱くなってしまった。
スロー・ブルースの「ウォーキング・ザ・バック・ストリート・アンド・クライン」を入れ、遅いテンポの曲を3曲続けた後、一転して8ビートの曲へと突入。思わず立ち上がり踊り出さずにはいられない展開だ。ドラムのジェシーがステージ後に「君が気持ちよさそうに踊っていたんで、こっちも嬉しくなったよ」と言っていたが、嬉しいのはこちらの方である。見事に乗せられてしまった。
さて、ここで一応バンドは引き上げるが、すぐにアンコールに応え再登場。客席にご挨拶まわりをするサービスをみせて、予定を大幅に上回った約2時間にも及ぶステージを終了させた。ステージ前に言っていたように、ソロ作からの曲が中心で、いわゆる「スタンダード」は一曲もやらなかった。これも自信の現れなのだろう。
満足したけど、まだまだ聴きたい!そんな一夜であった。
2000年5月26日(金)
今日はMDを買いに秋葉原へ行く約束をする。インタビューを受けているカールを待っていると、目の前を菊田バンドのネリー・トラヴィスやシャノン・カーフマンなどが通り過ぎ、結構楽しめた。
そうこうしている内にインタビューを終えたカールがロビーに下りてくる。ドラムのジェシーも一緒だ。昨日の午前中には、彼ら二人だけでお茶の水まで歩いて行ったらしい。仲が良いのだろう。
さて、秋葉原へ行こう、と思ったら日本人の友達を持ち、日本の文化に興味があるというジェシーが表参道の「オリエンタル・バザー」というお土産屋さんに行きたいという。そちらの方が地下鉄を利用すると近いので「じゃあ、表参道から」と言ったら、カールの顔を見て「いや、秋葉原からでいいよ」と一言。あくまでもボスはカールなのである。
さて、秋葉原に着いたカールは、すっかり気持ちを固めていたらしく真っ直ぐに免税店のMD売場へと向かう。
めでたく、マイク入力でもデジタル録音が出来るという最新型のプレーヤーとマイクを購入。
今回は街頭販売に引っかかることなく総武線に乗り込み、代々木経由で原宿へ。切符も自分で買ったし、すっかり東京の交通機関に慣れたカールであった。

オリエンタル・バザーでは、ジェシーが箸、ゆかたなど数点を購入。外国人にありがちな派手なデザインの物をさけ、落ち着いた商品を選んでいた。ソロ3作目の裏ジャケの写真もジェシーが撮ったそうで、そういうセンスを持ち合わせたヤツなんだろう。
翡翠を奥さんにプレゼントしたいと言っていたが、あまりの値段の高さに断念。しかし、一晩考えた彼は、翌日に自力で表参道まで行きゲットしてきたそうである。
さて、それぞれお望みの物を手に入れた二人とホテルに戻り、カールの部屋で話をすることにする。
と、そこには数種類の(お菓子の)「カール」が置いてあった。ファンの人(M&Iの方?)にプレゼントされたそうである。何種類もあるのに、よりによってカールが掴んだのは「梅味」。
「これは、どんな味だい?」
「う〜ん、プラムだけどなあ...」
「旨いかなあ?」
「やめた方がいいと思うけど...」
「やめろ」と言われると余計に手を出したくなるのは万国共通である。バリッと袋を開け、恐る恐る口に入れたカールは、酸っぱい顔をして絶句。大笑いする我々をよそ目に、秋葉原で購入した例の器具で袋を閉ざすカールであった。
「カール。初めて会った時のことを覚えているかい?」
「う〜ん、忘れちゃったなあ」
「ずいぶん無愛想だったぜ」
「あの頃は、S.O.B.のハードなスケジュールで疲れていたんだよ。南米を6週間だろ。ヨーロッパへ3週間行って1日だけシカゴに戻って、今度は日本。殺人的なツアーの連続だった...」
「S.O.B.をやめて良かったね」
「うん、ラッキーだったよ」
カールはインタビューなどで「S.O.B.は、ビリーのバンドである。彼のスタイルに合わせて演奏せねばならず、自分のやりたいように出来なかった」「自分のバンドが持てて、今は自由にやりたいように演奏が出来る」と語っている。
しかし、私の前では決してビリーの悪口は言わない。色々あったのであろうが、15年間寝食を共にしたのは事実だし、彼のおかげで現在の自分があるという事実をしっかりと認識しているのであろう。
「昨日のショーは最高だったね」
「みんな喜んでくれたようで嬉しいよ」
「明日も、バディを蹴散らすようなショーをやって欲しいな」
「バディは有名なブルースマンだぜ。たぶん俺のことを知っている人なんて日本には10人位しか居ないんじゃないかなあ。本当の意味で俺のことを分かってくれてる人なんてヒロだけじゃないか?俺達が良いショーをやったら、きっとオーディエンスは喜んでくれるだろう。でもな、その後バディの名前がコールされたとたんに全員総立ちさ。そんなもんだよ」
「いや、カールのファンは日本にも多いよ。そりゃあバディの方が有名なのは確かだけど、きみのショーを心待ちにしている人もいっぱい居るんだぜ」
「う〜ん...。でも、これだけは言えるよ。今度日本に来ることが出来たら、確実に俺のファンが増えているだろうね。3回目には秋葉原なんか歩けないほどになってるかもな、ハハハ!とにかく明日も全力でプレイをするよ。Big
Showだ!」
と言いながらギターをつま弾くカール。
突然、S.O.B.でもやっていたタイロン・ディヴィスの「アー・ユー・シリアス」を歌い始める。
「きみは、S.O.B.の頃にタイロンの曲をやることが多かったね」
「うん、ティーンネイジャーのころ流行っていたし、俺は大好きだった。実際彼のバンドにいたこともあるんだぜ」
「エエー!そんな話し初めて聞いたよ!?いつ頃いたの?」
「う〜ん、昔のことだからなあ。たぶん1976年頃だと思うよ。アルバート・キング・バンドに入る前の話だよ」
バイオによると71〜77年までは陸軍に所属し、その後ルイジアナ州警察、刑務官を務めていたらしいので76年というのは彼の勘違いだと思うが、タイロンのショーのオープニングのシーンを忠実に再現してくれたし、70年代後半か80年代初めあたりにタイロン・バンドに所属していたのは事実だと思う。
「俺がヤツの名前をコールするんだ。ミスタァ〜、タイロ〜ン・デイヴィィィ〜ス!!って感じでな。で、ヤツが登場するとおネエちゃんやオバさん方がギャ〜!って大騒ぎさ。でもな、ヤツは体中キンピカの宝石だらけで、そいつが照明に反射して眩しいったらありゃしない。ハハハ!演奏どころじゃなかったぜ!」

カールがギターに熱中している間に、ジェシーに話しかけてみた。
「ジェシー、きみの歌はなかなかいいね」
「サンキュー。R&Bやソウルのバンドで歌っていたんだ」
「ドラムを叩きながらかい?」
「もちろん」
「何でカールのバンドに入ったの?」
「(チラリとカールを見て)ソウル・バンドじゃ食っていけないんだよ。ブルースなら少しは金になるんだ」
「俺が見つけてきたんだ。いいシンガーでいいドラマーだろ?」とカールが口を挟む。
ボスの前では遠慮しているのか、ただ微笑みを浮かべるジェシー。
「きみは、何歳なの?」
「39歳になったよ」
「ワオ!1961年生まれかい?それじゃ僕と一緒だ!」
「そうかい!4歳になる娘がいるんだ。僕の名前の後にcaを付けて、ジェシカって名前なんだ。11月には次の子が産まれる。名前なんて考えてないよ。どうせ男が生まれたらジェシー・ワッツ・サードになるんだし、女の子だったらその時考えるさ」
と言いながら、ジェシカちゃんの写真を嬉しそうに見せてくれる。
「娘に「1週間ツアーに行って来るよ」って言ったら「どこまで行くの?シカゴ?(彼はインディアナ州在住)」って聞くんだ。だから「もっと遠いところだよ」って答えたら「分かった!L.A.でしょ!」だって。地球儀で日本を教えてやったら「こんな所に行っちゃうの〜!?」って心配していたよ。ハハハ!!」

黙々とギターを弾いていたカールが、突然顔を上げ口を開いた。
「ヒロ。サムライって本当にいたのか?」
「???」
「ショーグンってどんなヤツだったんだ?」
「侍は130年位前までは実際にいたし、将軍は、まあ大統領みたいなものかなあ」
「今はサムライはいないのか?」
「いないよー!」
「う〜ん、映画で見たことがあるんだけど、本当にそういう人たちがいたのか疑問だったんだ」
その後カールは、軍人として行ったベトナム(18歳で従軍している)や朝鮮半島の38度線での話や、アンゴラでの危機一髪の話、ビリーと共にビッグ・バンドの一員として中国に行ったときの話などをしゃべり続けた。
ジェシーと私は眠くなってあくびを抑えることが出来なくなったが、彼の話は尽きようとしない。
S.O.B.時代の寡黙な彼とはあまりにもかけ離れていた。私の前だけクールだったのかも知れないが、ジョークを飛ばし、尽きることなく話を続ける彼の姿は、まるで別人のように感じた。
そう、まるで自由に大空を羽ばたいている鳥のように...。
そのことが音楽にも反映しているというのは、言い過ぎではないと思う。自由に自分のやりたいようにプレイ出来る喜び。「元S.O.B.」という形容詞や、「父親の友人がアルバート・キングで...」などという逸話はもはや必要がない。
彼はカール・ウエザスビーであり、彼らはシカゴで最もホットなカール・ウエザスビー・バンドなのである。
2000年5月27日(土)
きょうは、いよいよ日比谷野音でのブルース・カーニバルである。
予報では、雨は夜半になってから降り始めると言っていたが、今にも降り始めそうなあいにくの天気だ。
トップの内田貫太郎トリオが演奏を始める頃にはついに雨が降り出した。40分ほどの彼らのステージが終わると、いよいよカール・バンドの登場である。
司会の後藤ゆうぞう氏がコールをすると共にオープニングの演奏が始まる。今日もカールはバックステージからギターを弾きながら登場だ。ただし、単独公演の半分ほどの時間しかないために、早めに登場した。
会場からの声援がいっそう大きくなる。
「ほら、カール!きみの登場を待ち望んでいた人たちはこんなにもいるだろう」
カールは初めから飛ばした。ステージ狭しと左右に移動して、ファン・サービスに終始する。
あまりの熱演に、シールドは抜けるは弦は切れるはでトラブルの連続である。しかし、始動したバンドの勢いは留まることを知らない。ブルース・アレイでは失敗した「弦張りパフォーマンス」も見事に成功し、会場からの喝采を浴びる。ソロを廻されたポールも、ブルース・アレイの時より熱のこもったプレイを披露した。そのコミカルな姿に会場は爆笑の渦だったが、決して軽蔑の笑いではなく「なかなかやるじゃん!」という声援だった。
1時間が30分位に感じた。
いま始まったかと思ったら、あっという間に終わってしまったという感じだ。
いや、1時間はあくまでも1時間である。緊張感を保ち続け、私たちの心をしっかり掴んだ彼らのステージが、時間を短く感じさせただけなのである。
彼らは、私に約束したように、日本のブルース・ファンにBig Showを披露してくれたのだ。
彼らのステージが終わると、私はバックステージに移動した。次は大トリのバディ・ガイの登場だが、私には彼のステージは予想できた。最大限の敬意を表するが、いまの私にはバディのブルースは必要なかった。
裏に回ると、テッドとポールがまず出てきた。
「ショーは楽しんだかい?」
「イェーイ!もっとやってくれよ!」
「ふー、もうダメだよ...」
着替えても汗ビッショリのポールはおどけて言う。
そして、着替え終わったカールが出てきて4人で特設テントの下へ移動する。
「みんな君たちのショーを楽しんでいたぜ!」
「楽しんでもらえて嬉しいよ」
M&Iの方が、缶ビールを振る舞ってくれた。テッドに渡すと、何と一気飲みをしてしまった。
それを見ていたカールがビールに手を伸ばす。
「ヘイ!カール!!ダメだよ。我慢しろよ!」
私は叫んだ。
実はカールは糖尿病を患いドクター・ストップが掛かっていたのだ。この4日間、彼が酒を飲んだ所は一度も見ていなかった。
「....」
彼はジッと缶ビールを見つめ、自分と闘っているようにも見えた。
私は、彼の気持ちが痛いほど分かった。Big Showをやってのけたんだ。いま飲んだらさぞ旨いだろう。
「OK Carl, Cheers !!」
私たちは乾杯をした。いやー、ビールが旨い!
その時、ステージからはバディ・バンドによる「スウィート・ホーム・シカゴ」が流れてきた。
間髪おかず、ポールとテッドがブーイングをする。
「俺達は、こんな曲やらねえよ!これをやれば誰でも喜びやがる。そんなところで勝負はしないよ!」
カールはただ微笑みを浮かべているだけだった。
「今度のCDは6月発売だって言っていたねえ」
「そうだ。メンフィス・ホーンズやアン・ピーブルズが参加したご機嫌なアルバムだぜ」
私は、自分の思いを彼に話した。
「それも楽しみだけど、君たちはこのメンバーで録音をするべきだよ」
カールは、ニヤリと笑いこう言った。
「俺もそう思う。たぶんその次のアルバムはそうなるだろう。ライブ・アルバムだよ。Live In Chicagoさ」
「Really !? Great !!!」
その後、私たちは少し話した。
昨日はポールとテッドで日光に行ったらしい。東照宮の階段を見てポールが気絶しそうになった話を聞いて大笑いをした。
イチローは素晴らしいバッターで、2〜3年後にはメジャー・リーグに行くだろうと伝えた。
「明日は嵐が来るそうなので飛行機が飛ばないかも知れないよ」と言ったら、「娘と1週間も会ってないんだから、気が狂っちゃうよ」と真顔で答えていた。彼は末娘のタビアちゃんを溺愛しているのである。
いよいよ別れの時が来た。
私は、素晴らしい彼らのショーと、楽しい時間を共有できたことで胸がいっぱいだった。
4日前の再会の時と同じように、むさい男同士が抱き合い別れを惜しんだ。
「色々とありがとうな。感謝しているよ」
「こっちこそ!また会える日を楽しみにしているよ」
彼を乗せた車が出発しようとしている。
私は、すぐに再会しようと言う意味を込めて声をかけた。
「See ya soon !!」
また会おうぜ!
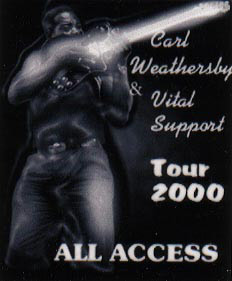
(2000年6月4日記)
(2000年6月6日改訂)
|